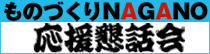| vol.111 | 「面白がる」 | 長野県テクノ財団ナノテク国際連携センター所長 若林信一 |
「君たちは生まれた時から山ばかり見てきただろう、動かぬ山を。もしあの山が海だとすれば、その向こうで何か新しいことが起こってはいないかと、毎日、気になって仕方が無くなるはずだ。」
入社した当時、社長がよく話していた「海」の話。すっかり見慣れたはずの信州の山々を前にして、時折ふっと思い出すことがある。
その頃の会社は国内の需要を受けて事業も経営も発展期に入りかけていたが、社長の目はすでに海外へ向いていた。
「我々は海外とも競争できる国際商品を目指さなくてはならない。良いものを作って世界が必要とする会社になろう。」
それが当時の社長の口癖だった。
高度成長期、ものづくりの現場は面白かった。とりわけ、新製品を開発するために新しい装置を導入して、試作を始めたときの緊張感は忘れられない。大変だ、大変だと言いながらも、やる気は十分、皆気合が入っていた。時には、やりたいことが幾つも重なり、興奮を抱えたまま徹夜明けの帰路についたこともある。
現場は、雑然としていたが、短い言葉のやり取りでコミュニケーションが取れていた。毎日のように起こる新しい事態にも敏感に反応し、そこで生まれた細かい工夫、アイディアは数えきれない。
以前、OSソフト Linux(リナックス)の生みの親、リーナス・トーバルズ(Linus Benedict Torvalds)の自伝書「JUST FOR FUN(それがぼくには楽しかったから)」という本を読んだことがある。その中で彼は、「ただ面白かったから夢中になってやっただけだ...」と語っていた。
この本には、「The Story Of An Accidental Revolutionary"偶発的革命の物語"」という副題が付されているが、自分にとって必要で、楽しいから作ったものが、結果として革命的な変革につながったというのだ。面白がる中で生まれ出るものには、端倪(たんげい)すべからざるものがある。
ひとから「オタク」だと馬鹿にされようとも、面白ければ止まらないし、可能性を否定することもないだろう。その無償の行為が大きな力を持つこともある。人間の持つ「面白がる」という特質は実に不思議なものなのだ。

(Helsinki大聖堂にて)
北欧フィンランド・ヘルシンキの若者が面白がって開発したOS Linuxは、山を越え、海を越え、時空を越えて、今も進化し続けている。
若林信一
長野県テクノ財団ナノテク国際連携センター所長
1949年長野県生れ 新光電気工業㈱にて取締役開発統括部長、韓国新光マイクロエレクトロニクス社長などを歴任。長野県テクノ財団ナノテク・材料活用支援センター長を経て2012年4月から現職。博士(工学)
http://www.tech.or.jp/

![[コラム]ものづくりの視点](/column/img/title.jpg)