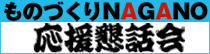| vol.119 | 技術はひよわな花か? | 長野県テクノ財団ナノテク国際連携センター所長 若林信一 |
この間(2012.10.8)の夕方、テレビを見ていたら、京都大学の山中伸弥教授のノーベル医学・生理学賞受賞のニュースが流れた。大変うれしかった。と同時に国際競争の激しさや研究費獲得の苦労がしのばれた。この後、文部科学省は直ちに今後10年に渡って、200億円から300億円の支援を行うことを表明し、国をあげてこの研究を後押しすることになった。これもタイミングのいい決定であった。しかし、現在の先端的な科学研究や技術開発には多額な費用が必要であり、これにあたる研究者の数も、少なくとも200人、300人の体制が求められる。数人の研究室で教授を中心にコツコツと研究を重ねて研究成果を積み上げると言う時代は、とうに過ぎ去ったようである。
今では科学研究の成果が産業的な成功に結び付くことは常識である。しかし、専門家としての科学者という職能集団が誕生したのは19世紀後半であり、その活動は自然界の謎を解きたいと言う好奇心に基づくものであった。この人たちの獲得した知識が産業的な成果に結びつくのは、主に20世紀に入ってからである。1935年のナイロンの開発は科学が産業や社会に大きな影響を与えることを示す象徴的なものであった。また、科学研究、技術開発の組織化と言うことではエジソン(T.A.Edison)の例があり、彼は当時だれも考え付かなかった多くの科学者、技術者を組織化して技術・商品開発を進めていた。彼の多方面にわたる発明はこういう組織化の上に成り立っていたのだそうである。国家的な意思で行なった研究開発にはマンハッタン計画があり、この結果は科学研究における科学者の倫理や社会、環境に与える大きな影響など、新しい問題を提出することになった。
こういうふうに科学的な成果が産業力や国家間の力の源泉にもなるようになると、単に研究者の好奇心、探究心に任せておけばいいというものではなくなる。しかし、科学的な発見は、やはり個人の好奇心、探究心にその源があり、それを大事に育て、尊重する環境がないと、その結果が成果として花開くことは難しい。研究者個人にとっての科学研究は成果に何の保証もない孤独な作業である。大した成果もあげられず、失意のまま人生を終えることもいくらでもある。こういう中での研究者は常にたとえ成果を出したとしても、誰にも評価されないのではないか、と言う怯えにも似た気持ちの中にいる。こういうひと達に期待するならば、物心両面に渡る支援も必要である。ようやく芽を出しかけた成果も冷水を浴びせたり、水をあげたりしなければ容易に枯れてしまうのである。科学や技術はいわば「ひよわな花」なのである。
iPS細胞の研究はこういう初期の段階をすでに乗り越えており、優れたアイデアと組織力で応用の方向に進んでいる。優れた研究の成果は「どの花見ても綺麗だな」と言う感じである。しかし、やっと開いた花であっても「開いたと思ったらいつの間にかつぼんだ」と言う例は決して少なくない。これを「つぼんだと思ったらいつの間にかひーらいた」と言う状態に持って行くためには、「ひよわな上に気ままでもある花」を励まし続ける環境が必要なのである。花が咲かなければ、当然実は結ばない。
若林信一
長野県テクノ財団ナノテク国際連携センター所長
1949年長野県生れ 新光電気工業㈱にて取締役開発統括部長、韓国新光マイクロエレクトロニクス社長などを歴任。長野県テクノ財団ナノテク・材料活用支援センター長を経て2012年4月から現職。博士(工学)
http://www.tech.or.jp/

![[コラム]ものづくりの視点](/column/img/title.jpg)