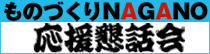| vol.78 | DTFの「カミワザ」 | 財団法人長野県テクノ財団 事務局長 林 宏行 |
「私たちの10年をプレゼントしたいのです。」
ミッション11日目、フランスでのDTFのプレゼンテーションが始まった。スクリーンには分水嶺から望む諏訪の地、そして薄っすらと浮かぶ富士山に、ブラインドから漏れて来た夕陽が重なった。
時計は既に17時半。当初予定されていたワークショップでは、この地の産業と振興策、立地環境の説明が熱心に行われたこともあって、昼食会と午後の工場見学を済ませてから、こちら側のプレゼンとなっていた。
指揮者小澤征爾氏がその名を知られるきっかけとなった歴史と文化の都「ブザンソン」(フランシュ=コンテ地域圏の首府)は、諏訪と同じく内陸部にあって、製糸から精密工業の街へと発展を遂げたフランス東部の都市である。近接するドイツやスイスとも経済的な繋がりが深く、とりわけスイスからは、時計をはじめとする精密部品を請け負っていた企業が多かった。だから日本が、時計や自動車で急成長を遂げてゆくあの時代に、ブザンソンは地域経済に大きな打撃を受けていたのだった。
そんな歴史もあってか、商工団体の方々の反応は、一様に硬い印象を受けた。担当者は、直接的に国の名を口にはしなかったものの、スクリーンには韓国、イスラエルの名の前に「日本」が書かれ、その影響を示す指標が写されていたし、医療や航空関係を手がける精密部品メーカー「Cryla」の工場視察では、地元メディアが待ち受けていて、「SUWA」からの訪問団をその歴史も踏まえて興味深そうにマイクを向けてきた。
さて、今日の平出正彦会長(株)平出精密代表取締役)はストレートだった。あえて構えた人の懐(ふところ)に飛び込むように"諏訪"の歴史にも触れ、そのうえでDTFの理念を訴えた。
DTFは、単に、それぞれの企業が作ったマイクロマシンを売り込むだけではない。省資源、省スペース、省エネを図るプロセスイノベーションを通して、地球と環境にやさしい新しい企業文化を発信しようとするものだ。
とりわけこの10年は、各企業にとっても厳しい歳月だった。だからこそ「失われた10年」などと俯(うつむ)いてはいられない。
「DTFは私たちの10年の成果なのです。それをプレゼントしにやって来ました...。」平出会長は繰り返し語った。
続いて立ったのは、㈱みくに工業・生産管理課長の真道一志(しんどうかずし)さん。"諏訪"の将来を担う若手の一人だが、昨夜、ミラノから乗り継いだチューリッヒ(スイス)でスーツケースが誤送されてしまい、降り立ったリヨン空港で受け取れないというトラブルに遭っていた。しかも届くのは早くて明日の夕刻だという。その真道課長、落ち着いた表情でパソコンを操作しはじめた。<プレゼン道具だけは肌身(はだみ)離さず持ちあるいていたのだ。>そして、超微細部品を巧みに摘んでパッケージへと充填していく「ハンドリング搬送装置」の動画が始まると、会場の視線がスクリーンへと集まり、フランス語で何やら囁く声も聞こえ始めた。
そしてラストは、㈱ダイヤ精機製作所・生産部長の武井持(たけいたもつ)さん。
「これは人の髪の毛です。私どもはこれに0.05mmの穴をあけ、注射針を作る研究をしています。人の細胞でできた注射針は体(からだ)の拒否反応も少ないのです...。」
両腕を広げ、笑顔で語る武井部長が繰り出したのは「高速高精度スピンドル」と穴の開いた髪の毛の断面。まさに「髪技」(カミワザ)だ。
プレゼンを終え、立ち上がろうとするDTFメンバーに向かって声がかかった。
「明日もフランスにいるのか?どこへ行けば続きが聞ける?」
それまで、神妙な顔を見せていた「Cryla」のゼネラルマネージャー、 ティエリー(Thierry Bisiaux)氏らが笑顔で立ち上がっていた。

(2011/02/09 ミッション11目、ブザンソンより)
林 宏行
財団法人長野県テクノ財団 事務局長
1963年下伊那郡喬木村生まれ。長野県商工部振興課、総務部地方課、市町村TL(課長)、下伊那地方事務所地域政策課長などを経て、2010年4月から現職。http://www.tech.or.jp/
| vol.77 | 「12²+1」(12の二乗プラス1) | 財団法人長野県テクノ財団 事務局長 林 宏行 |
DTF欧州販路開拓ミッションより③
ミラノ市内からバスで北西へ向う。海抜ゼロのベネチアはもとより、イタリア北部はアルプスを望むところまで緩やかな丘が続く。街を抜けハイウエイを1時間ほど走ると視察先の「Quanta System」社はあった。周辺は、工場やオフィスが区画を分けているが、5分ほど歩けばゴルフ場もある。快晴、2月上旬とは思えない穏やかな陽射しに、コートはバスに置いてきた。
オフィスの正面は、全面がミラー硝子となっていて、冬の空を映して碧い。その空に大きく「Quanta.System」と赤いゴシックの文字が浮かぶ。そして、オフィスに入るといきなり「12² +1」という文字がデザインされた赤いポスターが目に飛び込んだ。12×12=144、+1=145??...その不思議な計算式の意味など聞く間もなく会議室に案内され、プレゼンテーションの準備が始まった。
見渡すと、製造現場とは思えぬほどの美しい内装に目を奪われる。通路や部屋のドアノブ、窓枠などにまでそれぞれ独自のデザインが施してあった。ことに曲線や白に黒、赤の色使い、輝きを放つ金属の使い方が巧みだ。ユニフォームは支給されていないという従業員は皆オシャレで相対的に若々しく見えた。
さて、開放的でスタイリッシュなテーブルに着いた研究開発マネージャーのフェラーリオ(Fablo Ferrario)氏は先ず、背にした大きな液晶画面に「DNA Laser Technology」という文字を映しながら、1985年の創業以来、レーザー一筋に魂を注いできたことがQuanta社の真髄だと強調した。
研究者であった彼の父(現社長)は、レーザーこそがこれからのイノベーションの中心となると信じ、他に目もくれず取り組んできたという。以来、一代でこのポジションを築くことになるが、驚くことに今も25%もの成長を見込むそうだ。確かにレーザーの活用分野は、産業、軍需から医療、そして美容へと拡がっている。
しかし課題もある。それは、急成長を続けるQuanta社であっても、大半がOEM生産に依存せざるを得ないということだ。製造されたレーザー装置は、それぞれの国で許認可を持つ既存の医療メーカーに名を付され販売される。ある意味ではリスク排除の側面も否めないが、医療分野における規制のハードルと医療現場の閉鎖性、新規参入の難しさを物語ってもいるようでもあった。
開発担当のアレキサンドラ(Alessandro)を横におき、社の技術の先進性を熱く語る若きフェラーリオ。幾たびも口にした「DNA」という言葉には、その技術とともに、彼の父に対する思いと誇りを強く感じた。
そして処はオフィスに程近いゴルフ場のレストラン。私はテーブルにつくと、通訳の栗林かおるさん(高島産業(株))を介しながら、横に座ったフェラーリオに「12² +1」の意味を聞いてみた。そして彼は、アレキサンドラと顔を見合わせながらこう言った。
それはイメージ。「12」はPresident(プレジデント)の刻んできた「時」を、「2乗」は「未来」を、「+1」とは「プラスα」...つまり「人間性」とでもいうか、計算によって得られないひとつの「オマケ」というか...つまり、イメージ、デザインなんだ...。
そういえばイタリアの風土もデザインも、「計算」では得られない、人間的なエネルギーの現れのように感じた。笑顔で応える若い二人に、何ごとにも直ぐに計算しようとしてしまう私たちの頭の硬さをちょっぴり恥ずかしく、そして、ひとマネではない、人間味のある何か一つを加えることが今の日本には必要なのかもしれないとおぼろげに思った。フェラーリオおすすめのパスタと粉チーズを待ちながら...。
 (DTF研究会欧州販路開拓ミッション9日目。ミラノより)
(DTF研究会欧州販路開拓ミッション9日目。ミラノより)
林 宏行
財団法人長野県テクノ財団 事務局長
1963年下伊那郡喬木村生まれ。長野県商工部振興課、総務部地方課、市町村TL(課長)、下伊那地方事務所地域政策課長などを経て、2010年4月から現職。http://www.tech.or.jp/
| vol.76 | 「鉄パイプ」のゆくえ | 財団法人長野県テクノ財団 事務局長 林 宏行 |
DTF欧州販路開拓ミッションより②
何処まで行くのだろう、バスは街から離れ、ハイウエイに入った。実は、今日の企業視察は、相手の都合で急きょ変更になっていた。だから、行き先の会社の概要を知る由もなく、ましてベネチア郊外の、閉じられたシャッターの目立つ工業団地に降り立った時は、ここに暮らす通訳のジェシー(Giuseppina)さえ戸惑いの顔をみせた。
そして、大柄な男性に案内されたのは、旧いガレージ風の鉄工所だった。奥から鉄と油が匂ってくる小さな事務所を抜けると、薄暗い作業場が現れた。作業員は全員男、かつ無愛想でマイペース。作業台のまわりに鉄パイプなどの部品や工具が雑然と置かれていて、全体が流れ作業になっているのかもわからない。ユニフォームなどなく、手袋もはめていない。工作機械は古くシンプルなものが多く、鉄パイプを曲げたり切り落としたりする時の金属音と研磨機の音がガレージの天井を揺らし、時に溶接の火花だけが青く眩しい。一人ひとりの持ち場には、サッカー選手や女優のブロマイドが張られたりしている。

さて、名刺交換した後、大柄なセールスマネージャーのジョズエ(Giosue)氏が次に案内したのが、鉄工所と道を隔てたところに並ぶ建物。最初に「Givas」という会社名が青く書かれたショールームに入る。ジョズエ氏によると、Givas社は、1983年に分社化によって誕生したらしい。親会社は1967年に創業したVassilli社であり、ともに工場を並べている。ここまできて、Givas社が医療・介護用ベッドを、Vassilli社が車椅子を作っている会社だということ、そして、あの鉄パイプが共有の部品であるということが分かった。
ベットや椅子が並ぶショールームには、統一感のあるデザイン家具も備えられていた。医療用のベッドは、病院からのオーダーをもとに作る。床擦れ防止や寝起きの介助など医師が求める機能に応えなければならないが、使う側にも配慮して、専属のデザイナーを置いているという。大きなドアを向こうには作業場があり、高く積まれた部品棚やダンボールの間で、明るいクリーム色のベッドが組立てられていた。
続いてVassilli社の工場に入る。車椅子の骨格らしいフレームにカラフルな色が塗られていく。自動制御された機械などなく、ひとりひとりが工具を手に持つ。背もたれのクッションも生地からここで縫い上げる。三人の女性が踏んでいるミシンは昭和時代のブラザー製だった。工程を奥にたどるにつれて、車椅子には、様々な機能が組み込まれていく。なかには、筋萎縮性障がいの人でも操作できる最先端のコントローラーもある...。
そして此処までやって来ると、誰もが気づき始める...。そう、ここで作られているのは、一つひとつが異なるサイズと色彩を放つ『ひとり一葉』のベッドや車椅子だったのだ。
「人々の病や障がいは様々。だからこそ、一人ひとりに求められる機能と、心を満たすことのできるデザインでなければならない」と、社長のベルトルッチ(Bertolucci Vassilli)氏は力を込めた。そういえば、職人たちがチェックしていた伝票は、あたかもカルテのようだった。
「人が人のために、人のペースでモノを作る。ヒューマンマニファクチャリングなんだよね、ここは...。」高島産業(株)のアソシエイトマネージャー栗林かおるさんがそっと呟いた。
ラストは、車椅子のショールーム。様々な機能の解説を耳にしながらの試乗会となった。その時、我々とは反対のドアを開けて、ひとりの老人が立つのが見えた。家族の椅子を受取りにきたのだろうか、従業員から使い方を聞いている。しばらくして老人は、毛糸の帽子で目頭をそっと押さえ、従業員に握手を求めた。車椅子を静かに両腕で抱えた老人の、前の自動ドアが開くと、隣のガレージから鉄パイプの金属音がすべり込んできて、春まだ浅いベネチアの太陽に、車椅子のピンクの鉄パイプが照らされていた。
 (DTF研究会欧州販路開拓ミッション6日目。立春のベネチアより)
(DTF研究会欧州販路開拓ミッション6日目。立春のベネチアより)
林 宏行
財団法人長野県テクノ財団 事務局長
1963年下伊那郡喬木村生まれ。長野県商工部振興課、総務部地方課、市町村TL(課長)、下伊那地方事務所地域政策課長などを経て、2010年4月から現職。http://www.tech.or.jp/

![[コラム]ものづくりの視点](./img/title.jpg)