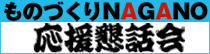| vol.59 | ものづくりのDNA(逝きし世の面影) | 長野県テクノ財団ナノテク・材料活用支援センター長 若林信一 |
「技術で勝っても事業で負ける...、技術で勝って事業でも勝つビジネスモデルに転換しなければならない」...産業構造ビジョン2010(産業構造審議会産業競争力部会報告書)における「問題意識」の件(くだり)だ。
デジタル技術の普及と成長市場の新興国への移行に伴い、日本のモデルは、高い技術の象徴でもあった半導体はもとより、携帯電話、液晶テレビ、カーナビといったボリュームゾーン※まで韓国や中国メーカーに持って行かれ、世界シェアを失いつつある。
すでに、「技(わざ)」の属性は、「ひと」から「装置」へとシフトしている。数々のノウハウが詰め込まれ、完成度の高さを要求される半導体も、製造装置を買えば世界中の何処にあっても、ほぼ同じ品質と性能のものを作ることができる。そして最近は、技術者が集まれば必ず、「何をつくればよいのか、我々の生き残る道はどこにあるのか」いう悲鳴ばかりが聞こえてくるようになった。
にもかかわらず、中国人などの、とりわけ富裕層からは、高くても日本製品が欲しいという声を耳にすることもある。この内在するギャップを今日のモノづくり産業は抱えているともいえる。
「通商白書2010」に登場するアジアの中間所得者層の消費実態調査では、こんな見方を示す。
「日本製品の置かれた現状についてみると、調査対象、の都市全てにおいて、品質、信頼感、技術力が優れているというポジティブなイメージが抱かれている。注目すべきは、品質や技術に次いで評価されている項目として、「現代的」、「デザインがよい」など感性的イメージが挙げられる点であり、これらを付加価値に変換した商品作りが求められている。」と。
ところで、外国人の残した記録から明治末期までの日本文明を見つめなおした『逝きし世の面影』(渡辺京二著平凡社ライブラリー)には、職人が受け継いできた「粋」なモノづくりのあり様が描かれていた。
たとえば、華族女学校教師として来日していたアリス・ベーコン(1858~1918)は言う。「安い版画、青や白地の手拭い、ありふれた湯呑みと急須、農家の台所で火にかけられるおおきな鉄瓶、こういったものがすべて、きれいで趣味がよい。...日本の職人は本能的に美意識を強く持っているので、金銭的に儲かろうが関係なく、彼らの手から作りだされるものはみな美しいのです。」そして、渡辺京二は「アメリカ人とっては「安価」と「粗悪」は同義語なのだが、日本ではもっとも低廉な品物に優美で芸術的なデザインが見出される...」と、逝きし日本の面影を偲ぶ。
ボリュームゾーンを失いつつある今日の日本が、品質と信頼度を辛うじて得ている背景には、粋で美しく、細部に目の届いた確かな職人技のDNAが、今もひそかに生き続けているからだ、と信じたい。そして、「技」の属性を「装置」から再び「ひと」へとシフトさせることが、再生のビジネスモデルにつながるのではないかとも...。
「私にとって重要なのは在りし日のこの国の文明が、人間の生存をできうる限り気持のよいものにしようとする合意とそれにもとづく工夫によって成り立っていたという事実だ」 渡辺京二の言葉が思い起こされる。
※ボリュームゾーン = 一番の売れ筋の価格帯。もっとも購買層の多い消費帯。
若林信一
長野県テクノ財団ナノテク・材料活用支援センター長
1949年長野県生れ 新光電気工業㈱にて取締役開発統括部長、韓国新光マイクロエレクトロニクス社長などを歴任。2009年5月から現職。
http://www.tech.or.jp/

![[コラム]ものづくりの視点](/column/img/title.jpg)