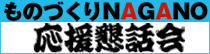| vol.120 | 信州~“物体O”による隔離地域の集合体~ | 長野県テクノ財団 メディカル産業支援センター 由佐 史江 |
前回まで、松本市から頂戴した「博物館パスポート」の利用について触れてきましたが、このパスポートの1年間という有効期限もついに切れてしまいました。段々に信州で暮らすことにも慣れてきたのかなあ、と、思えることも増えてきたような。
「信州に慣れたのかも」と、思える一例は「山の高さ」です。出張、帰省などで関西方面へ出かけることもあるのですが、その際、車窓から見える風景に、名古屋を過ぎたあたりから「あら?」と違和感を抱くように。山々の連なりに、思わず「低っ!」と、びっくりしてしまう。
奈良県の実家から、生駒山(標高642mの山)がキレイに見えるのですが、それが私にとっての「山」の基準。生駒山を「高いなあ」と、思って育ってきましたのに、今やペッタンコに見えてしまいます。これぐらいなら、越えてみようかなあ・・・、という気にさえなります。同じ日本人でも、「山」と言われてイメージするものは、地域によってかなり違うのだろうなあ、と、妙に感心してしまいました。
せっかく松本に越して来たのですから、山登りを趣味の一つに、という気持ちはあるのに、なかなかその勇気が出てこない。原因は、その辺りにもあるのかも、と、思います。「まあ、ちょっと越えてみようかな」と思える高さを基準に生きてきた人間にとって、桁違いに高い山を見てしまうと、「まあ、ちょっと」と気楽にも思えないし、山の向こうの世界には興味と共に、なんだか「全く見えないもの」への恐怖も感じてしまう。
これは、一昔前だと尚更だったのではないでしょうか。ここ信州では、山を越えて「向こう側」へ行くことは、今の世界を捨てることを意味する、それぐらいの覚悟が必要だったように想像します。
現在の仕事を通し、南は伊那・飯田、北は長野・上田と、広い広い「信州」を体感しております。同じ「信州」でありながら、山を越えると、全く違った「独自の文化」が各地域で栄えていることが良くわかるようになってきました。その体感からか、最近、私の中で信州をイメージする際、「物体O」という言葉が浮かんできます。
「物体O(オー)」とは、故小松左京さんの短編小説です。突然出現した高さ二百キロ、直径千キロにも及ぶドーナツ型の"異様な物体" Oによって、大阪を中心とした一帯が隔離されてしまう、というようなお話しだったと記憶します。「物体O」により、「外」との交流が遮断された区域。「信州」が「山脈」という小さな「物体O」に隔離された地域の集合体のように思えるのです。
「物体O」に隔離された人々は、外との交渉が基本的に「不可」であるため、自分たちで何とかしなければ、という道を選びます。信州の各々の地域も「輸入」という発想よりも「自分たちで作る(=「ものづくり」へ発展)」ことが自然であり、また、「自分たちで!」という結束力も強い。その歴史が地域毎の個性を生み出しているのではないか、と、広い県内を移動しながら感じております。
ただ「物体O」が提供したものは「ものづくりの精神」や「地域の個性の豊かさ」だけではないようです。外との交渉に「物体O」により制限を受けたため、異文化間の交流そのものが特別であったことは、「独自性」には強いのだけど「融合する」ということへの戸惑いも大きいのかなと、思います。
最近は「産学連携」、「コンソーシアム」や「クラスター」など、一昔前には聞かれなかった言葉がもはや定着。「協力関係を築きながら生み出して行こう」という発想が普通のものとなりました。グローバル化という流れも「融合性」に同調し、「一人で何ができるのか」ではなく、「みんなで何ができるのか」を考えなければいけない時代にあると思います。
メディカル産業支援センターでは、県内企業の医療機器産業への参入を支援しておりますが、医療機器の分野では「よきパートナーを見つける」ということが大事だと、日々の活動の中から実感いたします。「医療機器産業」という「新しい分野」へご参入いただくには、それだけでもエネルギーが必要な上、信頼できるよきパートナーをみつけ、かつ、「自分たちは何に貢献できるのだろう」と考える自主性も強く求められます。薬事法による規制など、医療機器産業参入にはただでさえ障壁が多いのに、さらに超えるべき問題が次々と出てくるようでは、参入に躊躇しても当然かと思います。
でも、まずは、「出会うこと」が基本なのではないでしょうか。「出会わなければ始まらない」というとてもシンプルなことが、結局解決の糸口になっていくように思います。
当センターでも、セミナー・フォーラムの開催や展示会出展などを通し、「出会いの場」の提供につとめております。是非、この機会もご活用いただき、「情報収集」のみならず、「よきパートナーが見つかった」という前進へつなげていただければ、と、強く願いながら企画しております。
由佐 史江
長野県テクノ財団 メディカル産業支援センター
メディ・ネットコーディネータ(公益財団法人長野県テクノ財団メディカル産業支援センター)
自然科学博士。医療系出版会社出身。バイオ系ベンチャーでの研究経験あり。平成23年度より現職。
| vol.119 | 技術はひよわな花か? | 長野県テクノ財団ナノテク国際連携センター所長 若林信一 |
この間(2012.10.8)の夕方、テレビを見ていたら、京都大学の山中伸弥教授のノーベル医学・生理学賞受賞のニュースが流れた。大変うれしかった。と同時に国際競争の激しさや研究費獲得の苦労がしのばれた。この後、文部科学省は直ちに今後10年に渡って、200億円から300億円の支援を行うことを表明し、国をあげてこの研究を後押しすることになった。これもタイミングのいい決定であった。しかし、現在の先端的な科学研究や技術開発には多額な費用が必要であり、これにあたる研究者の数も、少なくとも200人、300人の体制が求められる。数人の研究室で教授を中心にコツコツと研究を重ねて研究成果を積み上げると言う時代は、とうに過ぎ去ったようである。
今では科学研究の成果が産業的な成功に結び付くことは常識である。しかし、専門家としての科学者という職能集団が誕生したのは19世紀後半であり、その活動は自然界の謎を解きたいと言う好奇心に基づくものであった。この人たちの獲得した知識が産業的な成果に結びつくのは、主に20世紀に入ってからである。1935年のナイロンの開発は科学が産業や社会に大きな影響を与えることを示す象徴的なものであった。また、科学研究、技術開発の組織化と言うことではエジソン(T.A.Edison)の例があり、彼は当時だれも考え付かなかった多くの科学者、技術者を組織化して技術・商品開発を進めていた。彼の多方面にわたる発明はこういう組織化の上に成り立っていたのだそうである。国家的な意思で行なった研究開発にはマンハッタン計画があり、この結果は科学研究における科学者の倫理や社会、環境に与える大きな影響など、新しい問題を提出することになった。
こういうふうに科学的な成果が産業力や国家間の力の源泉にもなるようになると、単に研究者の好奇心、探究心に任せておけばいいというものではなくなる。しかし、科学的な発見は、やはり個人の好奇心、探究心にその源があり、それを大事に育て、尊重する環境がないと、その結果が成果として花開くことは難しい。研究者個人にとっての科学研究は成果に何の保証もない孤独な作業である。大した成果もあげられず、失意のまま人生を終えることもいくらでもある。こういう中での研究者は常にたとえ成果を出したとしても、誰にも評価されないのではないか、と言う怯えにも似た気持ちの中にいる。こういうひと達に期待するならば、物心両面に渡る支援も必要である。ようやく芽を出しかけた成果も冷水を浴びせたり、水をあげたりしなければ容易に枯れてしまうのである。科学や技術はいわば「ひよわな花」なのである。
iPS細胞の研究はこういう初期の段階をすでに乗り越えており、優れたアイデアと組織力で応用の方向に進んでいる。優れた研究の成果は「どの花見ても綺麗だな」と言う感じである。しかし、やっと開いた花であっても「開いたと思ったらいつの間にかつぼんだ」と言う例は決して少なくない。これを「つぼんだと思ったらいつの間にかひーらいた」と言う状態に持って行くためには、「ひよわな上に気ままでもある花」を励まし続ける環境が必要なのである。花が咲かなければ、当然実は結ばない。
若林信一
長野県テクノ財団ナノテク国際連携センター所長
1949年長野県生れ 新光電気工業㈱にて取締役開発統括部長、韓国新光マイクロエレクトロニクス社長などを歴任。長野県テクノ財団ナノテク・材料活用支援センター長を経て2012年4月から現職。博士(工学)
http://www.tech.or.jp/
| vol.118 | 強力「触」地域 ~県外からみた長野県2~ | 長野県テクノ財団 メディカル産業支援センター 由佐 史江 |
先の寄稿で、松本市から頂戴した「博物館パスポート」について触れました。この「博物館パスポート」を利用しながら、松本市内の色々な美術館、博物館を訪問させていただいています。今回は、「松本市立考古博物館」「四賀化石館」を訪れた際、感じたことについて述べたく思います。
県外出身、と記してきましたが、私は奈良県の出身です。それなりに考古学について知識を得る機会には充実した県で育ったつもり、なのですが、その立場から「松本市立考古博物館」の展示スタイルには、新鮮さを覚えました。
「展示品」はショーケースの向こう側にあるもの。大事な「宝物」として、息を殺して「見るもの」だと思ってきました。「展示品に触れる、なんてことはあり得ない」というのが、私の中では常識でした。
それが「松本市立考古博物館」では、「ご自由に!触って!触って!」と、触れることを推奨、かなり身近に展示されています。触ってはダメらしいものも、展示品と自分の間にガラスの仕切りなんてないので、ギリギリまで近づけますし、真上から覗き込むことだってできます。(縄文土器の内側が、あんなにスムーズに整えられている、とは知りませんでした。縄文時代の技術の高さ、繊細さが、よくわかったように思います。)
「四賀化石館」も同じく、触ることができました。見た目ではわからない重量感、凹凸などを肌で感じることができて、非常に楽しかったです。
展示品を「見ること」と、解説文を「読むこと」という視覚からの情報で納得するべきところに、「触ること(触覚)」が素直に付加されたスタイル。この「松本市立考古学博物館」「四賀化石館」での経験から、「手で触ることが大事」という信州気質が垣間見えたような気がしました。そこには、「百聞は一見にしかず」を超えて「百見は一触にしかず」という素地があるように思います。
「触らないとわかった気がしない」という角度で捉えると、なんとなく「頑固な信州人」の顔が、私の脳裏に浮かび上がりもしますが、この「手の感覚が大事」ということも、「ものづくり」の精神が育ってきた土台の一つなのではないでしょうか。
今は「触」に対して、大きく揺れ動いている時代です。実物を触らずにネットを通して買い物が出来る社会となり、「セカンドライフ」という言葉も、日常のものとなってきました。しかし、その一方で、「実物に触れる」ということの重要性が失われたわけではありません。「触」から離れるからこそ、「触」の重要さを認識できる、という傾向もあるかと思います。
メディカル産業支援センターからも、海外の展示会への出展を支援する事業を展開しておりますが、例えばドイツのデュッセルドルフで開かれる世界最大の医療機器関連見本市MEDICA(COMPAMED併設)へは、昨年度で約130,600人の来場があった、と報告されています。デュッセルドルフ市の人口は約60万人。デュッセルドルフ市内のホテルでは許容できないぐらいの人間が、ドッと押しよせ、一気に人口密度が上がったかのような状況が想像できます。展示会の目的はそれぞれですので、簡単には言えませんが、それでも「実物あります!」という呼びかけに、これだけたくさんの人が世界中から反応するわけです。
グローバル化に伴い、「自己表現」が適切にできているのかどうか、問われる時代です。その上で「触」の変化にどう対応するべきなのか、ということも大事なポイントのように思えます。常識的なこと、自然なこと、というのは、当事者にはその優れた点がなかなか見えないものですが、そこを掘り下げると、他者にとってはものすごいヒントとなるものが隠されているかもしれません。
無意識のうちに「触」に対し高い理解のある信州から、何か発信できることがあるのではないか。信州の「ものづくり」の現場を見学しながら、そんなことを感じています。
由佐 史江
長野県テクノ財団 メディカル産業支援センター
メディ・ネットコーディネータ(公益財団法人長野県テクノ財団メディカル産業支援センター)
自然科学博士。医療系出版会社出身。バイオ系ベンチャーでの研究経験あり。平成23年度より現職。

![[コラム]ものづくりの視点](./img/title.jpg)